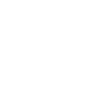この障害は、患者の気分と活動水準が著しく乱されるエピソードを繰り返すこと(少なくとも2回)が特徴であり 、気分の高揚、エネルギーと活動性の増大を示す場合(躁病または軽躁病)と、気分の低下、エネルギーと活動性の減少を示す場合(うつ病)がある。
[解説] 「喜怒哀楽」という言葉がありますが、人間は”ロボット”ではありませんので、当然感情があります。うれしいこともあれば、時には悲しいこともあります。それはおかしいことではありません。ただ、その振れ幅があまりにも大きいと、何よりその方自身がとても精神的につらいですし、それによって日常生活、社会生活に支障をきたすことがあれば、二次的にその方の被害は大きくなります。そのようなレベルでの振れ幅があること(期間)を精神医学で「エピソード」と言います。
躁うつ病はその字が示す通り、躁+うつ、つまりテンションが上がったエピソードと下がったエピソードの両方を併せ持つものを指します。よって、その方の生涯において片方だけみられている時点では、躁うつ病と「確定」することはできず、少なくとも2回目以降でないと「確定」することはできません。
ここで「確定」と書いているのは、「推測」することはある程度可能だからです。それに関しては、後日のコラムになると思いますが記載します。
・・・(略)・・・躁病エピソードだけを繰り返す患者は比較的稀である・・・(略)・・・
[解説] 躁病エピソードのみでうつ病エピソードがない単一性の躁病が存在するかというと、基本的には「存在しない」と考えます。
よって、初回に躁病エピソードがある時点で精神科医が診察した場合は、「必ずうつ病エピソードが今後あるはず」と考えます。
また、患者さんに躁病エピソードの治療とともに、来たるうつ病エピソードへの準備、対応の重要性をお話します。
(次回に続きます)