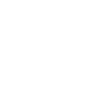F50.2 神経性過食[大食]症 Bulimia nervosa 【ICD-10】
神経性過食症は発作的に繰り返される過食と体重のコントロールに過度に没頭することが特徴で,患者は食べた物の「太る」効果を減じるために極端な方法を用いる.
[解説]名称の通り、過食があることがポイントです。過食したままですと、体重が増えていきますので、それを何とか回避しようと極端な手段をとります。
この用語は共通の精神病理をもつ点で,神経性無食欲症と関連した型の障害に限定して用いるべきである.
[解説]あくまで摂食障害の1つであるという認識です。
年齢の分布と性別は神経性無食欲症に似ているが,発症年齢はやや高い傾向がある.
[解説]若年女性に多いことは共通していますが、10代よりは20代以降に多いようです。
この障害は神経性無食欲症に続いて起きたとみなせることもある(しかし,この反対の順序で起こることもある).
[解説]両者はお互いに移行することがあります。
それまで無食欲症であった患者が体重の増加とおそらくは月経の再開によって改善したようにみえることがあるが,その後,過食と嘔吐を繰り返す治りにくいパターンが形成される.
[解説]神経性無食欲症の一部の方は、軽快していく過程で一時的に過食症に移行することがあります。必ずしも、全員が難治性になるわけではありません。
嘔吐の繰り返しによって電解質の異常,身体的合併症(テタニー,てんかん発作,不整脈,筋力低下),より高度な体重減少が生じやすい.
[解説]嘔吐によって身体のミネラルバランス(これを電解質と言います)が乱れやすくなります。そうすると、体調不良をきたしやすくなります。特に不整脈などは注意が必要です。
診断ガイドライン
確定診断には,以下の障害がすべて必要である.
(a)持続的な摂食への没頭と食物への抗しがたい渇望が存在する.
患者は短時間に大量の食物を食べつくす過食のエピソードに陥る.
[解説]何時間も食事を続ける方もいます。食べ物のことで頭がいっぱいになり、他のこと(仕事や学校のこと、日常生活のこと)を考える余裕を持てなくなります。嘔吐しやすくするために、あえて短時間たで大量に食べることもあります。
(b)患者は食物の太る効果に,以下の1つ以上の方法で抵抗しようとする.
すなわち,自ら誘発する嘔吐,緩下薬の乱用,交代して出現する絶食期,食欲抑制薬や甲状腺末,利尿薬などの薬剤の使用.
糖尿病の患者に過食症が起これば,インスリン治療を怠ることがある.
[解説]食べる一方だと肥満になりますので、それを回避するために、いろいろな方法をとります。自ら指を喉に突っ込んだりして嘔吐する方が最も多いです。頻繁に嘔吐していると、トイレで下を向くだけで嘔吐”できてしまう”ようにもなります。
(c)この障害の精神病理は肥満への病的な恐れから成り立つもので,患者は自らにきびしい体重制限を課す.
それは医師が理想的または健康的と考える病前の体重に比べてかなり低い.双方の間に数ヵ月から数年にわたる間隔をおいて神経性無食欲症の病歴が,常にではないがしばしば認められる.
この病歴のエピソードは完全な形で現れることもあるが,中等度の体重減少および/または一過性の無月経を伴った軽度ではっきりしない形をとることもある.
[解説]過食症は、過食だけでなく、拒食がみられることは少なくありません。その程度は人によってさまざまです。
(含)特定不能の過食
神経性食欲亢進
鑑別診断
(a)反復性の嘔吐を招くような上部消化管の障害(特異的な精神病理を欠く).
[解説]当然ですが、消化器疾患ですと、全く話が変わってしまいますので、それを除外しておく必要があります。
(b)より全般的なパーソナリティの異常(摂食障害はアルコール依存や万引きのような軽犯罪を伴うことがある).
[解説]起きていることの本質がパーソナリティのトラブルがメインなら、診断上はそちらが優先されます。
(c)うつ病性障害(過食症患者はしばしば抑うつ症状を経験する).
[解説]うつ病では食思不振となり、食事量が減ることが多いですが、実は逆に増えて過食になる方もいらっしゃいます。
| F50.3 非定型神経性過食[大食]症 Atypical bulimia nervosa この用語は神経性過食症(F50.2)の鍵症状としてあげられているもののうち,1つ以上が欠けているが,その他は典型的な臨床像を示す患者に対して用いるべきである. 最も一般的には,この用語は正常または過剰体重であっても,過食とそれに続く嘔吐あるいは緩下薬の使用を示す典型的期間を伴う患者に適用される. 抑うつ症状を伴う部分的な症候群も珍しくない(しかし抑うつ症状がうつ病性障害の診断を別個に正当化する場合, 2つの別個の診断を付けるべきである). (含)正常体重過食症 |
| F50.4 他の心理的障害と関連した過食 overeating associated with other psychological disturbances 苦悩をもたらす出来事に対する反応として肥満にいたった過食は,ここにコードする. とりわけ体重増加の素因のある患者には,死別,事故,外科手術,情緒的苦悩を与える出来事に続いて, 「反応性の肥満」が生じることがある. 心理的障害の原因としての肥満はここにコードすべきではない. 肥満によって患者は自分の外見に対して過敏になり,対人関係における自信を失うことがある. 体の大きさを過大に自己評価することがある. 心理的障害の原因となった肥満は,F38.- 「その他の気分(情緒)障害」,あるいはF41.2 「混合性不安抑うつ障害」,あるいはF48.9 「神経症性障害,特定不能のもの」などのカテゴリーにコードし,加えて肥満の型を示すためにICD-10のE66.-からのコードを付記する. 神経遮断作用のある抗うつ薬その他の薬剤の長期投与の副作用による肥満はここにコードされるべきではなく, ICD-10のE66.1 「薬剤性肥満」をコードし,薬剤を同定するために第Ⅹ章(外因)からのコードを付記する. 肥満はダイエットをする動機となることがあるが,その結果として軽い感情症状(不安,落着きのなさ,衰弱,刺激性),あるいは,まれに重篤な抑うつ症状(ダイエットうつ病)を引き起こすことがある. F30-F39またはF40-F48から適切なコードを上述の症状のために用い,さらにダイエツトを示すためにF50.8「他の摂食障害」を,また肥満のタイプを示すためにE66.-からのコードを使用する. (含)心因性の過食 (除)肥満(E66.-) 特定不能の過食(R63.2) |
| F50.5 他の心理的障害と関連した喝吐 vomiting associated with other psychological disturbances 神経性過食症で自ら嘔吐を誘発する場合以外に,解離性障害(F44.-)や心気障害(F45.2 :嘔吐がいくつかの身体症状の1つのことがある),および妊娠(情緒的な要因が反復性の吐き気と嘔吐を引き起こすことがある) の際に繰り返し嘔吐がみられることがある. (含)心因性妊娠悪阻 心因性嘔吐 (除)特定不能の吐き気と嘔吐(R11) |
| F50.8 他の摂食障害 other eating disorders (含)非器質性の原因による成人の異食症 心因性の食思不振 |
| F50.9 摂食障害,特定不能のもの Eating disorder unspecified |
307.51 神経性大食症 Bulimia Nervosa 【DSM-Ⅳ】
A.むちゃ食いのエピソードの繰り返し.むちゃ食いのエピソードは以下の2つによって特徴づけられる.
(1)他とはっきり区別される時間帯に(例:1日の何時でも2時間以内)、ほとんどの人が同じような時間に同じような環境で食べる量よりも明らかに多い食物を食べること
[解説]まず、食事量が多いのは必須です。
(2)そのエピソードの期間では、食べることを制御できないという感覚(例:食べるのをやめることができない、または、何を、またはどれだけ多く、食べているかを制御できないという感じ)
[解説]自分でコントロールできていないこと(感覚)も必要です。
B.体重の増加を防ぐために不適切な代償行動を繰り返す、例えば、自己誘発性嘔吐;
下痢、利尿剤、浣腸、またはその他の薬剤の誤った使用;絶食;または過剰な運動
[解説]食べ過ぎたことで太らないようにする行動をとります。最も多いのは吐くことです。
しばらく全く食べなくなる方などもいます。
C.むちゃ食い及び不適切な代償行動はともに、平均して、少なくとも3か月間にわたって週2回起こっている。
[解説]診断上は、3か月間以上で週2回以上が必要です。
D.自己評価は、体型及び体重の影響を過剰に受けている。
[解説]体重などが本人の望む数字ならよいですが、違う場合自己評価は非常にネガティブなものになります。
E.障害は、神経性無食欲症のエピソード期間中にのみ起こるものではない。
[解説]神経性無食欲症との区別のための項目です。
病型を特定せよ
排出型 現在の神経性大食症のエピソードの期間中、その人は定期的に自己誘発性嘔吐をする、 または下痢、 利尿剤、または浣腸の誤った使用する。
非排出型 現在の神経性大食症のエピソードの期間中、その人は、 絶食または過剰な運動などの他の不適切な代償行為を行ったことがあるが、定期的に自己誘発性嘔吐、または下剤、利尿剤、または浣腸の誤った使用はしたことはない。
[解説]DSM-Ⅳでは、このように排出型、非排出型で下位分類がありました。
307.51 神経性過食症/神経性大食症 Bulimia Nervosa 【DSM-5】
診断基準
A. 反復する過食エピソード。過食エピソードは以下の両方によって特徴づけられる。
他とはっきり区別される時間帯に(例:任意の2時間の間の中で)、ほとんどの人が同様の状況で同様の時間内に食べる量より明らかに多い食物を食べる。
そのエピソードの間は、食べることを抑制できないという感覚(例:食べるのをやめることができない、または、食べるものの種類や量を抑制できないという感覚)。
B. 体重の増加を防ぐための反復する不適切な代償行動、例えば、自己誘発性嘔吐;緩下剤、利尿薬、その他の医薬品の乱用;絶食;過剰な運動など。
C. 過食と不適切な代償行動が共に平均して3ヵ月間にわたって少なくとも週1回は起こっている。
D. 自己評価が体型および体重の影響を過度に受けている。
E. その障害は、神経性やせ症のエピソードの期間にのみ起こるものではない。
[解説]基本的にはDSM-Ⅳとほとんど同じですが、C項目が週2[解説]1回と変更されています。
該当すれば特定せよ
部分寛解:かつて神経性過食症の診断基準をすべて満たしていたが、現在は一定期間、診断基準のすべてではなく一部を満たしている。
完全寛解:かつて神経性過食症の診断基準をすべて満たしていたが、現在は一定期間、診断基準のいずれも満たしていない。
[解説]DSM-Ⅳにはなかった分類です。
現在の重症度を特定せよ
重症度の最も低いものは、不適切な代償行動の頻度に基づいている(以下を参照)。そのうえで、他の症状および機能の能力低下の程度を反映して、重症度が上がることがある。
軽度:不適切な代償行動のエピソードが週に平均して1~3回
中等度:不適切な代償行動のエピソードが週に平均して4~7回
重度:不適切な代償行動のエピソードが週に平均して8~13回
最重度:不適切な代償行動のエピソードが週に平均して14回以上
[解説]こちらもDSM-Ⅳにはなかった重症度分類です。回数に応じて変化します。